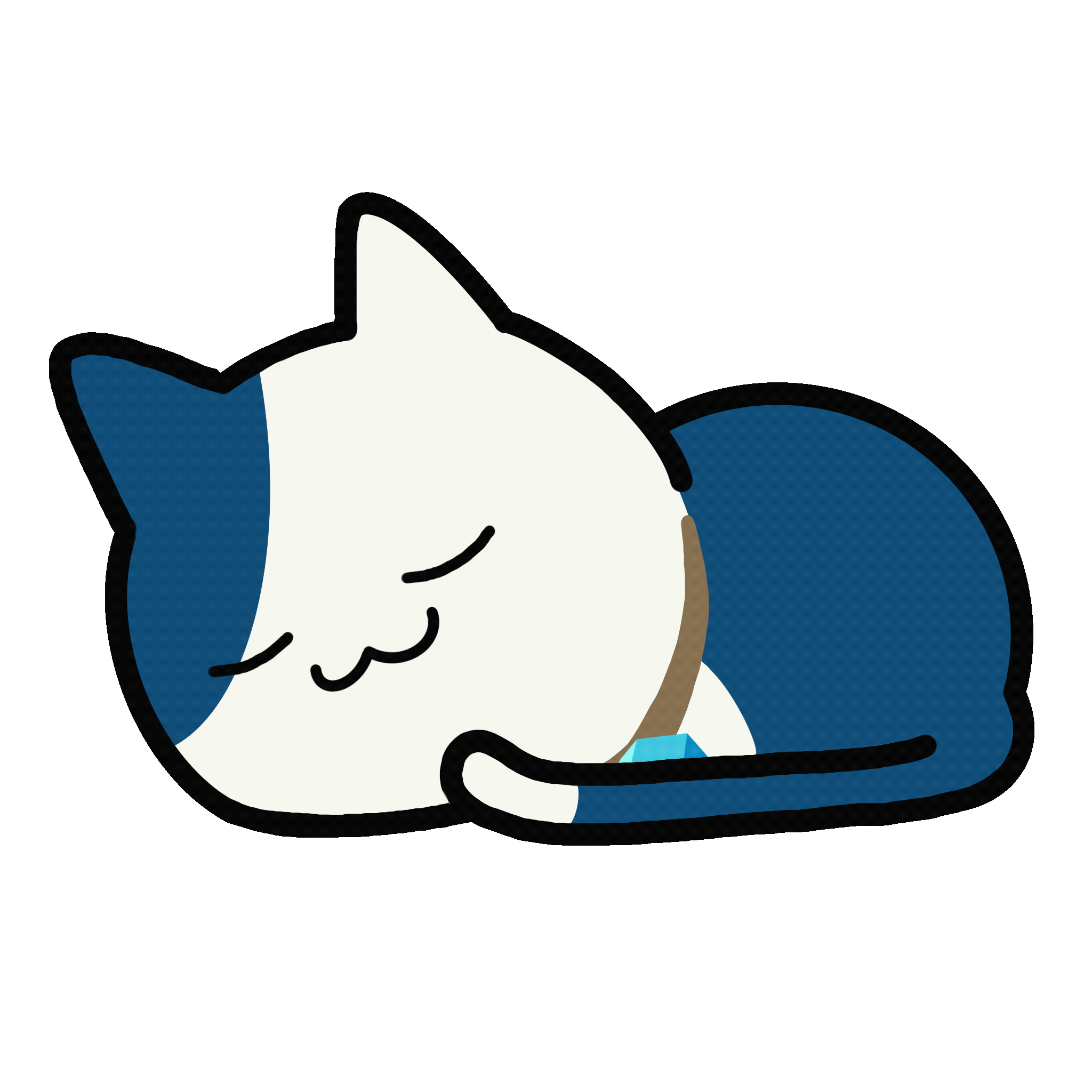システム開発の契約形態と登場する契約書 ~実際このユースケースではどうなるの?~
はじめに
ラズレイトの主たる事業はお客様のためにシステム開発を行うことです。
一口にシステム開発といっても、
- 開発手法はアジャイルなのかウォーターフォールなのか
- 開発工程は一括で全て行うのか、部分的な支援となるのか
など、お客様のビジネスや作りたいもの、ご要望によって、さまざまなお仕事の仕方があるかと思います。
システム開発をご依頼されるお客様に、弊社とご契約いただく際にどのような形態で、どのような契約を締結するのかがイメージしやすくなるように、システム開発を行う際の契約形態や必要な契約書をまとめてみました。
この記事で分かること
お客様がシステム開発をご依頼される際に、下記のイメージを持っていただけることが目的です。
- どんな契約形態があるのか
- どういう契約を結ぶべきか

契約形態
まずは典型的な契約の形態を見ていきます。
システム開発をご依頼いただく際、システム開発という業務を委託していただくことになります。
つまり、大きな枠で言うと業務委託契約を締結することになります。
この業務委託契約は民法上、「請負契約」「委任契約」「準委任契約」に分類されております。
請負契約
「企業が成果物の完成を約束する契約により、業務をアウトソーシングし、請負人は期限までに契約どおりの成果物を納めて、報酬を得る」という契約となります。
納期を取り決め、そこまでに成果物責任を負う。というのがポイントです。
委任契約
「当事者の一方が法律行為をして相手方に委託し、相手方の承諾後に効力が生じる」という契約です。
行為を実行すれば債務の履行となる点が請負契約との違いです。
準委任契約
委任契約の内容は法律行為を行うことでした。対して、法律行為以外の行為を委託する場合、準委任契約となります。
システム開発は法律行為ではありません。つまり、システム開発において、行為自体の依頼を依頼される際は、準委任契約となるのです。
つまり、システム開発を依頼される際は、請負契約もしくは準委任契約のどちらかを一般的には締結することとなります。
準委任契約には更に分類が…
ややこしいのですが、更に準委任契約の中には履行割合型(民法648条の2第1項)と成果完成型(民法648条2項・3項)があります。
履行割合型
委託事務の遂行にかかった工数や時間を基準として報酬が支払われます。成果完成型とは異なり、成果物の納品や成果目標の達成は報酬の発生要件ではありません。
月何時間稼働などでどれくらいの報酬と決め、開発や技術支援をするなど、SES(System Engineering Service)でよく締結される形です。
成果完成型
委任事務の履行により得られる成果物の納品や成果目標の達成に対して報酬が支払われます。
業務の終了に対して報酬が支払われると言う点で、請負契約との違いが分かりにくいですが、あくまで準委任契約なので、成果物責任はありません。
納品された成果物の種類、数量、品質に不備があった場合に直ちに契約不適合責任は負うことはありませんが、不備を解決するために適切な措置を取る必要があります。
工数ではなく、成果に対して契約したいが、請負契約のように業務全体を依頼するよりは一部の業務を依頼したい際に検討するのが良いかもしれません。
どのような時に選択すべきか
ざっくりと、以下のような基準が目安になるかもしれません。
やることが明確で業務全体の完成を依頼したい。 | →請負契約 | |
柔軟に業務を依頼したい。 or 一部の業務を依頼したい。 | →準委任契約 | |
明確な成果物が決まってない、それを一緒に考えたい。 都度柔軟に作業を依頼したい。 | →履行割合型 | |
成果物は明確、時間の確保というより完成をお願いしたい。 請負契約を結ぶほどではない。 | →成果完成型 |
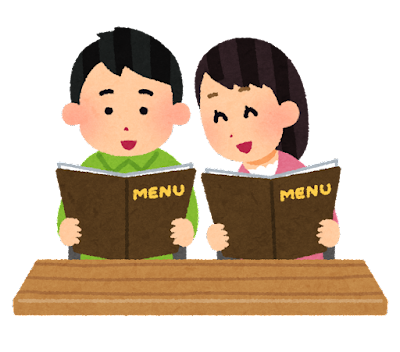
契約書
次に、システム開発いおいて一般的に登場する契約書を見ていきます。
NDA(秘密保持契約)
「Non-Disclosure Agreement(秘密保持契約)」は、取引を行う上で知った相手方の営業秘密や顧客の個人情報などを取引の目的以外に利用したり、他人に開示・漏えいしたりすることを禁止する契約のことです。
基本契約書にも秘密情報の取扱いについての項目はありますが、契約締結の前に、見積や提案を行います。この段階でお客様の業務情報やシステムについてご共有いただく必要がある際に、事前に締結しておくケースが多いです。
基本契約書
継続的取引全体に適用される基本事項の合意をします。B to B 取引の多くは継続的な取引ですが、逐一網羅的な契約書を作成していると、取引コストが増大してしまいます。そこで、あらかじめ基本事項を合意しておくことで、その後の取引について簡易な合意で済ませるようにするのです。
基本契約書で基本的な契約のベースを作っておくと、それ以降、注文書に開発対象や期間を示し、個別契約として扱うなどすることで、都度契約するコストを下げることができます。
工程ごとに発注を分ける場合や、長期的にお付き合いさせていただく場合など、継続的な発注を行う際に締結させていただくことになるかと思います。
ただし基本契約を結ぶ方が両者にとってコストが高い場合、個別契約のみで済ませるケースもあります。
この基本契約において、請負契約か準委任契約なのかなどの契約形態で、記載されるべき内容が変わります。
個別契約書
基本契約書に基づいて具体的なプロジェクトやサービスに関する詳細を定める契約書です。
プロジェクトのスコープ、納期、成果物、料金、サービスレベル、技術仕様など、具体的な取り決めを含みます。
前述の通り、基本契約書でベースの大まかなルールを定めた上で、実務的には、注文書などの明細で成果物をリストアップし、納期や金額を記載することで、個別契約とみなすことがあります。 必要に応じて、仕様書などを添付することで、詳細な成果物対象を明確にする場合もあります。
保守契約書
システム開発後の保守やサポートに関する契約書です。通常、システム開発プロジェクトが完了した後も、システムの運用や保守が必要となります。その際、クライアントとシステム開発会社の間で保守契約を結ぶことが一般的です。
保守範囲や期間、料金について定めます。

ユースケース
では、実際のユースケースの例をいくつか挙げて、どのような時にどのような契約を結んでいくことになるか、見ていきましょう。
比較的小規模な開発、企画から開発終了まで一括の請負
以下のような、比較的に小規模な開発で、企画〜開発終了まで契約を分ける必要のない場合、個別のソフトウェア開発委託契約書だけでもいい場合もあるかもしれません。
- 小規模なWebサイト・アプリケーション
- 簡単なLINEアプリケーション
- イベント用に向けて短期間だけ使うアプリケーション
- PoC(概念実証)用のプロトタイプ
ただし、実際にはシステム開発は単発で終わることはなく、追加の機能開発や改修が必然的に発生しうるものです。この場合でも、ベースとなる大まかな基本契約を結んで、個別契約を注文書などの記載で省略する方が、結果的に楽な場合が多いことが考えられます。
また別途、システムを稼働させ続けるには保守契約を結ぶ必要があります。
大規模なウォーターフォール開発
システム規模が大きく、要件定義→設計→開発→テストなどと、開発段階を分けるウォーターフォール型の開発の場合、基本契約は必ず結んでおいた方がいいでしょう。
その上で、工程ごとなどで契約を分割し、個別契約を締結します。
また、工程の性質ごとに、契約形態も適切なものを選択することも考えられます。
例えば、要件定義や結合テスト・受入テストの支援フェーズは、明確な成果物が決まっていないので、準委任契約が適しています。開発や単体テストフェーズは、請負契約で納期や成果物などスコープを定めておくのが、クライアントとって安心できるメリットがあります。
アジャイル
DXの時代においては、ますます激しくなるビジネス環境の変化への俊敏な対応が求められます。そのDX推進の核となる情報システムの開発では、技術的実現性やビジネス成否が不確実な状況でも迅速に開発を行い、運用時の技術評価結果や顧客の反応に基づいて素早く改善を繰り返すという、仮説検証型のアジャイル開発が有効となります。
アジャイル開発を選択する場合、請負開発とは性質上相容れない部分があるため、より柔軟に業務を行える、準委任契約を締結するのが良いでしょう。
準委任契約に対する基本契約を締結し、期間や工数、報酬を定めた、一定の期間ごとの個別契約を締結します。
IPA(独立行政法人 情報処理推進機構)が、アジャイル開発のプラクティスやモデル契約書を掲載しています。
アジャイル開発はスピード感を持って不確実性を内包したまま開発を行えるメリットがあり、ウォーターフォール型より、「システムを開発する」ということ自体の性質に適した開発手法といえます。
ただし、システム会社に開発を丸投げするのではなく、クライアント側にオーナーシップを強く持った、プロダクトオーナーを設置する必要があります。また、クライアント側も含めたスクラムイベントも頻繁に行い、クライアントと開発会社で、より密接なコミュニケーションを取っていく必要があります。
必然的に、スコープや期限の管理などの難易度も上がってしまうため、システム規模や人的コスト的なリソースの状況に応じて、最適な開発手法と契約形態をご相談させてください。
ラボ契約
ラボ契約とは、ある一定期間の間、お客様の専用チームを用意し開発を行う形態のことです。
実際の契約形態としては、準委任契約となります。
ただし、人を固定したSESとは違い、チーム単位で準委任契約を締結することになります。
ラズレイトではアジャイル開発を行う際、ラボ型での準委任契約もおすすめしています。
弊社内の開発チームとして統制が取れることでお客様の負担を下げ、より柔軟で効率的な対応が可能になります。
アジャイル開発以外でも、お客様の社内に情報システム部や開発部が無い、またはリソースが足りていないため、社外システム部・パートナーとして時間を確保させて欲しい!など、固まった成果物を定めず柔軟に対応することができますので、ぜひご検討ください。
業務の一部の依頼や調査の代行など
小規模な一部の業務の依頼や、技術的な調査の代行、ちょっとしたツールの作成など、ご依頼いただく場合もあります。
そのような場合、準委任契約を結ばせていただくのが良いかと思います。
履行割合型か成果完成型かは、内容に応じて相談させていただきます。
大きな開発や要件定義の前に、技術調査や、信頼関係の構築として既存システムの改善などをご依頼されることも歓迎しております。

おわりに
システム開発における、契約形態や登場する契約書の種類、実際のユースケースでどのような契約を締結することになるかを見ていきました。
少しでもイメージが湧く参考になりましたでしょうか?
個別の状況に応じて最適な形態は変わってくるため、ラズレイトでは実際のお客様や案件にとって最適な方法を検討させていただきます。
ご相談お待ちしております!